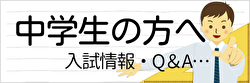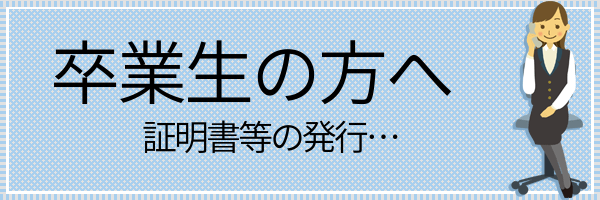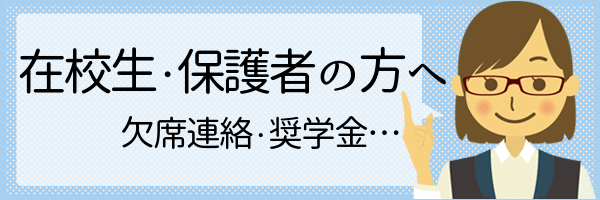学校長あいさつ

本校校長の橋本有司と申します。私自身、本校第37回卒業生であります。よろしくお願いいたします。
本校は、小浜藩校である「順造館」を始まりとし、1897年(明治30年)を創立の年と定め、創立127年目を迎える県内でも有数の歴史と伝統を誇る学校です。卒業生は3万人を超え、その卒業生の誰もが「異質なものに対する理解と寛容の精神を養い、教養豊かな社会人の育成を目指す」という本校の教育目標を大切に心に刻んでいます。本校の教育活動は全てこの目標のもとに行われています。
第3期スーパーサイエンスハイスクール(SSH)(R6~R10)、マイスターハイスクール(R3~R5)の指定を受け、若狭地域の資源や直面する課題、自然科学や興味関心ごとに対する疑問などを生徒自らが課題として設定し、実験や調査、データサイエンスなどを通して探究していく探究学習に力を入れています。その成果が、SSH研究発表会や小学校中学校出前講座、「宇宙食サバ缶」の開発などにあらわれています。また、各教科学習においても、学習内容に対して一人ひとりが疑問や課題意識を持ち、主体的に学んでいくことを大切にしています。
また本校は、一人ひとりや地域社会の「ウェルビーイング」(多様な幸せ)の実現に向け、対話を中心とした教育活動により幸せや豊かさを実感できる心の育成を図っています。海外に連携校(アメリカ「マーセッドカレッジ」、台湾「暖暖中等教育学校、台湾海洋大学」、フィリピン「デ・ラサル・リパ高校」)を持ち、高校生や大学生、研究者の方と多くの生徒が海外交流をしています。このような取り組みによって生徒自身の新たな発想、新たな価値観の創出を支援して世界で活躍できるような人材の育成を目指しています。
今後とも本校の教育活動に一層のご理解とご支援を賜りますようよろしくお願いいたします。
令和6年4月
福井県立若狭高等学校 校長 橋本有司